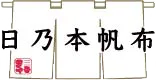【Vol.2】米沢市民のソウルフード 米沢らーめんの秘密
私はネコ。鞄屋に居候するネコだ。
鞄屋は「日乃本帆布」という。
山形県米沢市に工房を構え、今年は創業40週年を迎えた。一つひとつ手づくりで、鞄屋にはいつも、ミシンとトンカチの音が。
手元が見えずともその音を聞いていると、職人のモノづくりに注ぐ真っ直ぐな気持ちや、使い手にかける愛情などが伝わってくるようだ。
あの鞄はどんな人と巡り会えるのだろうか。
工房の側は直営店になっている。
ここ米沢は上杉の城下町で、
観光客が上杉公園周辺の散策途中に偶然見つけて立ち寄ってくれたりする。
今日は夫婦で訪れたお客さんが、ショルダーバッグを手に取り、
ファスナー式のものにするか、かぶせ型にするか、
ちょっとレトロな金具式もいいなと、どのデザインにしようか迷っている。
それぞれバックは色のレパートリーもたくさんあって、なかなか決まらない。
「インターネットでも購入できますよ」
って教えたようだけれども、
奥さんは運命でも感じたようなきらきらした目で夢中になっている。
どうしても今日手にしたいらしい。
散々迷って、ショルダーの取り外しができるトートバックに決めたようだ。
すると奥さん
「もう一つ相談なんですけれども、この後米沢ラーメンを食べて帰りたいんですが、
この店とこの店、どっちがおススメですか?」と質問。
「どちらもおいしいお店ですよ。
こちらはスープがあっさりしていて、こっちはチャーシューが・・・」
今度は米沢らーめんのお店選びで迷っているようだ。

鞄もラーメンも、その人の好みだろう。
こちらがこうと言っても、食べる人が、使う人が変われば、きっと正解は異なるはずである。
日乃本帆布の鞄は長年の定番商品から「スタッフのこんな鞄が欲しいな」から生まれるNEWフェイスまで様々。
どれも職人が丹精込めて仕上げた自信作だから、お客様の用途と好みから提案することができる。
しかし米沢市内にはラーメン店がたくさんあって、地元民はそれぞれのお気に入りのお店が。
聞く人によっておススメ店も異なるのだ。
あれ、そもそもみんなが何気なく食べている米沢らーめんって、どんなラーメンなんだ?

「米沢らーめんの特徴は『麺』なんだよ。」
「水分をたっぷり含んだ『多加水(たかすい)』と呼ばれる製法でつくるもので、
小麦粉をこねるときに通常より多く水を加え、軟らかく練り上げている。
ストレートに切り出した麺は、職人が一つひとつしっかり手揉みをかけて、2~3日熟成。
独特の食感を持つ、手もみ縮れ細麺なんだ」
そう教えてくれたのは、米沢麺業組合会長の加納正仁さん。
米沢市内にある「羽前路 あいづや」を営んでいる。
多加水麺というのは、麺がのびやすくなるためどうしても太麺になる傾向にあって、
細打ち縮れ麺というのは、全国的にも特異な形状の麺なのだそうだ。
米沢らーめんの歴史と文化を守り、発展させていくために発足された
(協)米沢伍麺会では、「米沢ら~めん」と登録商標し販売している。
ということは、麺が米沢らーめんなら、
スープはどんなものでも米沢ラーメンということになる?
「そういうことだよね。
ただ、基本は煮干しと鶏ガラの合わせ出汁スープでつくる、
毎日食べても飽きがこない中華そばが定番。
配合はそれぞれの店によって異なるし、近年は豚骨や鰹などスープ素材も多様化していて、
その店ならではの味でお客様のおもてなしをしているよ。
麺もスープもつくる人によって異なるラーメンになるから面白いよね」。
なるほど、奥が深い。


しかし、なんでここ米沢にはラーメン屋さんがこんなにもたくさんあるのだろうか。
「小麦粉文化が盛んな北緯37度線の話はしってる?」と加納会長。
聞けば北緯37度線上には、米沢のほか、福島県の喜多方市、世界では北朝鮮、イタリアなんかが位置し、
パスタや冷麵、ラーメン、そばなど様々な麺文化が発達している緯度なんだとか。
「ここも北緯37度線界隈ってことなんだよ」と加納会長は笑う。なんだか都市伝説のようだ。
そもそもの歴史を遡れば、関東大震災で東京が大混乱になった大正12年の数年前、
横浜の中国人街で、中国料理を日本人向きにアレンジした中華風そば「支那そば」が生まれ、各地に普及していったらしい。

そして米沢にもチャルメラをふきながら屋台を引く3,4人の中国人が現れる。
この支那そばは予想外に売れ、中国人は米沢で店を構えるまでになったとのこと。
同じころ、市内にあったカフェー「舞鶴」の調理人常松恒夫(つねまつみちお)さんが、東京築地の政義軒で修行を積み、
支那そばを米沢で販売する最初の日本人らーめん職人となった。
中国人がもたらし、常松さんが発展させたらーめんは、昭和9年頃になると爆発的な勢いで米沢中に広がったそうだ。
そしてどの店にも、自宅の近く、会社の近く、お気に入りの味、そのお店の味が好きなファンがいて、
ごひいきさんに支えられてきた加納さんはいう。
「米沢麺業組合は会員も70軒ほどいたけれども、現在加盟店は27軒。
担い手がいなくて惜しまれながら辞めていく店が多くあるのが現状。
今度は担い手の育成や人手不足などの課題があるよね」。
米沢らーめんは毎日食べても飽きのこない、シンプルでどこかほっとする優しい味だ。
米沢を離れた人は、お盆やお正月に帰ったとき、食べなれたラーメンを食べてほっとするらしい。
「観光に訪れるなら、どのお店も味が統一ではありません。
きっとお好みの1杯が見つかると思いますので、何度も米沢を訪れてもらいたいですね」。
日乃本帆布に訪れるお客様の中にも、
この米沢本店に何度も足を運んでくださる方が多くいる
ここの帆布は硬くて厚くて頑丈だから、型崩れすることなく、色の変化が楽しめる。
またしっかりしているから、鞄が自立し使いやすい。
もちろん布が硬いということは、職人がミシンをかけるのも力や技術が必要で、
大量生産ができないのだけれども、使う人を想っていつも楽しそうにつくっているものだから、
きっと工場のとなりにある本店に来る人にはそれが伝わるんだろうな。
色、形、サイズの種類の豊富さに加え、職人がいるからこそお客様の要望でタグや、
ショルダー、ポケットを追加してくれることも。
「本店は選ぶ楽しさも魅力です。迷ってもいい。買わなくてもいい。
まずは遊びにくる感覚で来てもらえたら」
とスタッフは言う。
大いに迷いながら、わくわく選んで、自分好みを見つける、そんな人生も悪くない。

協力/米沢麺業組合 参考文献/米沢麺業史
米沢らーめんについては、ホームページおいしい麺!米沢麺業組合をご覧ください。
(https://0141men.com)
各お店のこだわりや想いも紹介されています。
著/キクカク企画 阿部薫